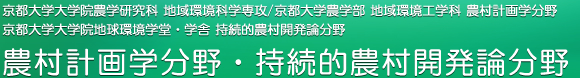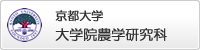研究室の方針
農村計画学とは・・・
農村というと,水田,畑,山林などの間を小川が流れ,農家住宅が点在するのどかな田園風景を思い浮かべていただけると思います。しかし最近では,高速道路が走り,住宅団地やドライブイン,ガソリンスタンドといった都会的施設が見かけられる所も多くなってきました。また一方では,過疎化や高齢化が進み,耕作されないで放棄されている農地や管理不十分な山林もみられるようになっています。そのため,童謡「春の小川」に唱われているような,静かで素朴な農村の風景が失われつつあります。 このように,「心のふるさと」としての農村の個性が失われていくことは,何か一抹の寂しさを感じます。
農村地域は,農業や林業という生産活動が営まれる重要な空間であることはもちろんですが,面積的には国土の97%を占め,豊富な生態系を育んでいる自然空間であるとともに,国民の4割近くが住んでいる重要な生活空間でもあります。そのため,農村に住む人々の生活の安全を守り,快適で豊かな生活環境を保障することも必要となっています。さらに今日では,都市に住む人々にとっても余暇活動などに利用される身近な空間ともなっています。
そのため,将来にわたって自然と人間が共存しうる,豊かで美しい農村環境と,活力と魅力にあふれる農村地域を創り出す農村環境整備が重要な課題となっています。すなわち地域の自然環境を守りながら,農地の生産性の維持・向上と,快適性や安全性に富んだ農村の生活環境の整備が求められているのです。 農村計画学は,こうした農村地域の「将来像」を考える学問です。すなわち,快適農村の創造をめざして,多様化している人間活動と自然環境との関わりを分析し,将来にわたって自然と人間が共存しうる農村環境を創っていくための「計画」に関する学問です。
(先代のホームページより)

農村計画学の特徴
農村計画学という学問は比較的新しい学問分野であり,地域課題の解決に貢献するという実学的な特性を備えた学問分野です。いくつかの特徴をあげてみます。
1.農村計画学はプラグマティックで学際的な「雑科学」です
体系的な基礎理論があって,それを駆使して解決できる課題をさがし,解決する…これは通常の学問のスタイルです。しかし,計画学の場合は課題から発想し,それを如何に解決するか,解決に有用な道具(論理)を探し出してそれを組み立てるスタイル,つまり,解決すべき問題から発想するプラグマティック(実用主義的)なアプローチをとります。もちろん,現実の課題を解決するためには特定の個別分野だけでは不十分であることが少なくありません。このため,学際的なアプローチ,すなわち関連するいくつかの分野の知見を必要に応じて動員する必要があるのです。そして,計画学はいろんな分野の役立ちそうな知見を組み合わせるわけですから,一種の雑学であると言えます。ちなみに雑学という言葉を辞書で引くと,『広い分野にわたっている雑多な知識』とあります(小学館国語大辞典,1988)。しかし,計画学が一つの学問として成立するためには,単なる物知りとしての雑学ではなく,科学的な根拠に基づいて論旨が展開されねばなりません。つまり,計画学は科学的な手順を踏まえた『雑科学』なのです。
2.農村計画学は結果よりもプロセスを重視する学問です
計画学とはいい計画をつくるための方法論をあれこれ考える学問です。しかし,ここで何を基準に『いい計画』を判断するかというやっかいな問題があります。この点がクリアにならないと,どんな方法がいいかを明確に判断できないのです。では,『いい計画』とは『いい結果をもたらした計画』と考えていいでしょうか?答えはノーです。まれなことですが,ずさんな計画でも偶然うまくいくことがありますし,逆によく練られた計画でも環境条件の急変によりうまくいかないことが少なくないからです。計画の良否を事後の結果だけで判断するのではなくて,プロセス(計画づくりの手続き)の妥当性(最善の診断,最善の設計,適切な合意形成)で判断すべきなのです。このような考え方に基づく計画学はProcess-Oriented Planning(過程指向型計画論)と呼ばれます。
3.農村計画は地域再編計画です
農村計画は地域の問題を解決し,地域を変化させるためのものですが,決してニュータウン計画のようにプランナーが白紙の上に自由に描くべきものではありません。農山村地域には人と自然の共生システムが存在していますし,農村計画がそのような中で有効に作用するためには,そういった地域システムの特性を理解し,それに対する親和性に十分配慮する必要があります。つまり,農村計画は地域再編計画なのです。農村計画のプランナーは,さしずめ(家の)リフォームの達人といったところです。古くからある『いいもの』を活かし,それを徒に壊すことなく,新たに求められる機能を埋め込むことが求められているのです。したがって,地域システムをまずはよく理解することから始めなければなりません。
具体的な農村計画学の内容は,「農村計画学」の講義(農学部3回生対象,星野担当)で詳しくお話しすることにしましょう。農村計画学は新しい学問です。研究課題も山のようにいっぱいあります。あなたも我々と共にチャレンジしてみませんか?

教育研究の方針
本研究室を希望される学生・院生の皆さんに向けて,研究室の教育研究方針を何点かお話したいと思います。
1.問題意識の重視
問題意識とは,「事態・事象についての問題の核心を見抜き,積極的に追求しようとする考え方」(広辞苑)と言う意味ですが,なかなかピンときません。特に理科系の学生諸君はこの種のトレーニングの経験が乏しいこともあって,この問題意識という概念に馴染むまで少し時間がかかります。そして,問題というものが実は主体の主観的認識から生み出されたものである!という基本的事実にとまどいます。しかしながら,ここで多少時間がかかっても,自分自身の問題意識を確立してもらうように配慮しています。その方が皆さんのモチベーションが高まり,結果的には成長速度が向上するからです。
2.フィールドワークの重視
おそらく計画系の研究室ならどこでもこのような姿勢を持っているのですが,「常に現場から学ぶ」という意識をいつも忘れないように心がけています。現場には我々の研究課題がいっぱい埋もれています。また,解決の糸口さえも現場で見つかることが少なくありません。まさに,「問題は現場で起こっている」のです。足を使った現場調査やワークショップなど,フィールドワークと呼ばれる技法を重視しています。
3.社会工学的手法の重視
端的に言うと,我々の基礎は工学にあります。当研究室では,農山村地域に関わる様々な問題や社会事象を様々な工学的手法(数理的・計量的手法)により解明し,政策提言に結びつけるというスタイルを意識的に採用しています。この方針には「我々の得意分野を最大限に生かす」という戦略的な意味合いがあります。ただし,我々は「現実の課題を解決するという目的に沿ってもっとも適切な手法を選択する」という立場に立ちます。あくまで手法は解決のためのツールです。「手法を使いたいから,適当な課題を設定して適用する」という立場には決して与しません。この点は特に強調しておきたいと思います。
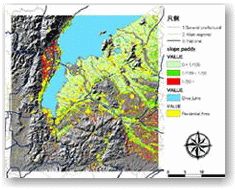
図 GISによる土地利用分析

図 住民参加型の計画づくり
4.自然科学と社会科学の融合をめざして
自然科学と社会科学の融合とはちょっと大げさですが,実際に現場の課題を解決する処方箋を描くためには,ものごとを総合的な観点からとらえる必要があり,結果的に様々な知識や理論が必要になります。研究者の都合?で学問分野はどんどん細分化されてきましたが,現場での問題解決は常に総合的な判断が必要とされています。現場レベルで考えれば,「自然科学と社会科学の融合」は避けては通れないことなのです。したがって,本研究室を希望する学生・院生諸君には,地域環境工学(農業農村工学分野)の基礎学の修得だけでなく,必要に応じて他の自然科学系分野や社会科学系分野にも手を広げる知的貪欲さを期待します。
研究室のあゆみ
農村地域の開発整備計画を担当する研究者,技術者養成という社会的要求に応じるため,1966(昭和41)年4月に農学部農業工学科の中に農地計画学講座が新設され,農村地域の調査,計画,整備に関する原理と諸技法について研究教育を担当することとなりました。これが本研究室の前身にあたります。初代教授として西口 猛先生(教授期間1967~1988),2代教授として高橋 強先生(同1988~2005)がそれぞれ講座(研究室)を担当されました。2007年4月からは星野 敏が着任しています。
これまでの研究室のあゆみと主な研究成果についてはこちらをご覧ください。