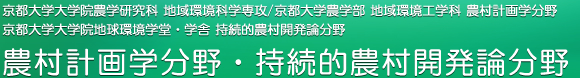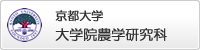研究室のあゆみ
京都大学農学部農業工学科は,農学部が創設された翌年の1924年(大正13年)に開設され,旧制では農林工学科として林学系2講座が含まれていましたが,基本的には農業土木系2講座,農業機械系1講座で運営されてきました。ところが,1960年代から始まったわが国の高度経済成長以来,わが国の農村は大きく変貌し,農地のスプロール化,農業用水の汚濁,過疎化の進行などにより,農業生産環境や居住環境に様々な弊害が生じてきました。そのため,農業の近代化,農業構造の改善による生産性の向上と土地・水資源の有効利用開発ならびに農業災害の防止などが国家的な見地から強く要請されるようになりました。農業の近代化・生産性の向上のためには農業の機械化,経営規模拡大のための農地の基盤整備ならびに農地造成が必要であり,また土地・水資源の有効利用開発のためには総合的な地域開発計画や農地計画が必要となります。
このような農村地域の開発整備計画を担当する研究者,技術者養成という社会的要求に応じるため,1966(昭和41)年4月に農学部農業工学科の中に農地計画学講座が新設され,農村地域の調査,計画,整備に関する原理と諸技法について研究教育を担当することとなり,翌年3月講座担当教授として西口 猛が着任しました。その後,農業生産基盤とあわせて農村の生活環境の整備を行う農村総合整備の重要性が高まるにつれて,研究の中心は土地利用計画や農村整備計画の原理とその策定手法の研究に移行してきました。当時は全国的にもこの分野の研究者は少なく,本講座のスタッフ一同はその草分け的存在として農村計画・農村整備の調査研究や事業の推進に指導的役割を果たすとともに,この分野の研究者・技術者の組織づくりとして農業土木学会農村計画研究部会の設立(1971年)やこれを母体とした農村計画学会の創立(1982年)に中心的役割を担い,学会の発展に貢献しました。1980年代後半からは環境保全の必要性の高まりから農業集落排水の研究にも力が注がれるようになりました。
本講座発足当初は教授1名,助教授1名,助手2名の定員でしたが,1981(昭和56)年大学院熱帯農学専攻が設置されたのに伴い,助教授北村貞太郎が地域計画論講座担当教授として転出し,助手定員1名を持ち出したため教官定員は3名となりました。1988(昭和63)年3月に西口が定年退官の後,同年4月高橋 強が講座担当教授となりました。1995年4月からは大学院重点化を目的とした学部改組により,農地計画学講座は地域環境科学専攻農村計画学分野に名称変更されました。
2005(平成17)年3月に高橋が定年退職しましたが,2007(平成19)年4月に神戸大学より星野 敏が担当教授として着任しました。
(先代のホームページより)
これまでの主な研究成果
本研究室は,農村計画学,特にフィジカル・プランニング(土地利用,物的基盤,施設にかかわる計画)の分野においてユニークな研究成果をあげてきました。主な研究成果を「京大農学部70年史」より示すと,以下のとおりです。
1.農業生産基盤の整備に関する研究
農業の労働生産性の向上や農業経営の近代化を図ることを目的として,1963年に圃場整備事業が開始されたが,水田は通常湛水条件下で栽培されるため地耐力が不足している場合が多く,暗渠による圃場排水の促進が緊急の課題であった。しかしながら,構造が未発達な粘土質水田ではただ暗渠を埋設しただけではその効果は十分に発揮されないことも多かったが,西口は,暗渠埋め戻し部の透水性が良好で作土亀裂と暗渠との水ミチが確保されていることが重要であるとして,暗渠疎水材としてのモミガラの特性に着目し,モミガラ壁式暗渠を提唱した。これは,透水性の大きいモミガラ壁によって集水することにより地表残留水や重力水を迅速に排除するというもので,多くの水田に適用され,その有効性が実証された。 また,山間の急傾斜地水田では地形的制約から事業費が高くなり圃場整備が遅れているが,急傾斜地では必ずしも長方形区画とする必要はなく,事業費節減の観点から等高線形区画が優れていることを示した。
2.農村整備計画策定手法の研究
農村地域は農業生産の場であるとともに国民の居住空間として重要な役割を担っているが,急激な都市化の進展と国民の生活様式の高度化に伴って都市と農村の生活環境の格差は著しく拡大し,都市に比べて立ち遅れている農村の生活環境の整備を行うことが重要な課題となった。しかしながらこれまでの農業土木学の研究では農業の生産性向上に主眼がおかれ,生活環境の整備技術やそのための計画策定手法については十分な知識が得られていなかった。本講座では積極的にこの課題に取り組み,1967年以来農村整備に関する調査研究(茨城県玉里村)や農村基盤総合整備パイロット事業調査(愛知県常滑市),緑農住区開発関連土地基盤整備調査(神戸市岩岡町)をはじめ,滋賀県守山町,中主町における調査研究等を通じて農村地域の土地利用,道路,施設配置等の農村整備計画の策定手法の確立につとめ,その後の農村整備事業の創設と推進に貢献した。
とくに整備要望の多い農業集落道については多くの事例調査に基づき集落形態と道路整備の特徴を整理し,整備指標を明らかにするとともに,集落形態による集落道の整備計画手法の提言を行った。この研究を端緒として後に今井敏行は農業土木学会奨励賞を授与された。農業集落排水については後述するが,西口は1977年以来農業土木学会計画基準改訂委員会農村環境整備部会長として農村整備計画の基準づくりに指導的役割を果たし,上記の研究成果は『土地改良事業計画指針・農村環境整備』(1990年,農業土木学会)に盛り込まれ,農村総合整備事業の推進に貢献している。近年では農村におけるアメニティ志向の高まりを受けて,滋賀県甲良町の潅漑排水事業において親水空間整備の必要性を提言するとともに,京都府八木町の圃場整備計画において景観保全や地域文化財保護の重要性を指摘している。
3.土地利用計画策定手法に関する研究
高度経済成長に伴って都市圏域が拡大してくると,都市的土地利用と農業的土地利用の競合が起こり,農地の無秩序な転用による優良農用地の蚕食が問題となってきた。いわゆる農地のスプロールである。そこで土地利用の秩序形成と優良農用地の保全のための土地利用計画の策定が重要な課題となってきた。そのため本講座では,1974年から滋賀県新旭町において土地利用計画策定のための適性評価手法に関する研究に取り組むとともに,全国の研究者が集まって1976年以来文部省科学研究費の補助を受けて行われた土地分級に関する一連の研究においても中心的役割を果たしてきた。これらの研究を通じてこれまでの農業経済的土地分級論を土地利用計画のための土地分級論へと発展させ,主成分分析を応用した地区分級と,数量化理論を適用した用地分級の手法を確立した。これらの成果は科学研究費の助成を受けて出版された西口監修・長崎・北村編著『土地分級』(1981年,農林統計協会)として集大成された。その後,用地分級に関しては評価者の属性や達観評価値の信頼性についてさらに研究が深められた。
これらの土地分級や土地利用計画策定のためには土地片の自然的社会的諸特性の把握と収集整理が重要である。本講座ではリモートセンシング技術を農村計画の研究に先駆的に導入し,ディジタル土地条件図作成の方法についても研究に着手した。この研究を契機として松尾芳雄(現愛媛大学)は後に農業土木学会奨励賞を授与された。一方,計画的な土地利用の実現を図るためには,農地の所有・利用者たる農家の利用意向を計画に十分反映させることが重要であるとの認識から,1982年以来京阪奈地域総合整備計画調査(京都府田辺,精華,木津町)等を通じて農家の土地利用意向を詳細に調査分析した結果,都市化の進んだ市街化区域内の農家でも6割程度の農地は今後とも農地として所有・利用したいとしており,10年以内に転用・売却したいと考えている農地は1割程度に過ぎないことを見いだした。こうした農家の土地利用意向の特徴を踏まえ,都市的土地利用の計画的整備創出と優良農地の保全を図っていくためには農業側の論理にもとづく土地利用計画の策定が必要であることを提唱した。この研究により,中西信彦は1988年農業土木学会奨励賞を授与された。
農村地域の土地利用は地域住民の生産や生活に密接に関連しているので,計画づくりへの住民参加も重要である。牛野 正は,住民が主体的に土地利用計画(あるいは総合計画)を策定することにより,実効性のある土地利用計画(あるいは総合計画)を策定するための計画手法として,神出方式を開発した。
4.農村地域の水質保全と農業集落排水の研究
農村社会における混住化の進展や生活様式の高度化は農村地域の水質汚濁を進行させ,農業生産および生活環境に様々な悪影響を及ぼすこととなった。そこで,都市に比べて特に立ち遅れている下水道の整備を推進することにより,農業用用排水の水質保全,農業用用排水施設の機能維持および農村生活環境の改善を図り,生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資することを目的として,農業集落排水施設の整備が行われるようになった。農業集落排水施設はし尿を含む農村集落からの生活排水を集めて処理する施設であり,その整備のためにはこれまでの農業土木学ではなじみの薄かった汚水処理に関する知識が要求されるが,本講座ではいち早くこの問題にも取り組み,流入汚水の変動特性,雨水流入の実態と対策,維持管理体制の課題など,農業集落排水特有の諸問題について多くの知見を得た。
とくに,農村地域の水質保全や閉鎖性水域の富栄養化防止のためには窒素・リンなどの栄養塩類の除去も重要であるが,多くの現地調査の積み重ねにより回分式活性汚泥法で間欠曝気運転を行うことにより高率窒素除去が可能であることを実証し,その運転管理方法を明らかにした。また,処理槽中に鉄接触材を浸漬することにより溶出した鉄イオンが汚水中のリンと結合してリン除去が可能になるという新しい処理技術を開発するとともに,前記回分式間欠曝気法と組み合わせた窒素・リンの同時除去技術の確立に成功した。これら一連の研究により西口は1988年に農業土木学会学術賞を受賞した。
その後,嫌気性腐食による鉄接触材の溶出速度に及ぼすDO濃度や有機物負荷の影響を明らかにし,鉄接触材の必要浸漬量算定方法に根拠を与えた。またオキシデーションディッチ法についても現地試験によりその処理特性と高率窒素除去のための運転管理方法を明らかにするとともに,嫌気性ろ床併用接触曝気方式の処理施設における高度処理の問題点として,微小後生動物の影響や汚泥管理などの重要性を指摘した。
長年にわたる農業集落排水処理とそれを基礎にした農村の生活環境整備に関する一連の研究が高く評価され,高橋 強(現石川県立大学)に対して2006年に農業土木学会学術賞が授与された。
(先代のホームページ内容に追記)
これまでに在籍された方々(50音順)
- 今井敏行
- 牛野 正
- 海田能宏
- 北村貞太郎
- 高橋 強
- 西口 猛
- 治多伸介