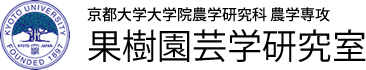研究室の紹介
果樹園芸学研究室の紹介
当研究室は,果樹園芸・園芸利用学を担う分野として1926年(大正15)年に設立されました.以来,一貫して果樹を研究対象として果実生産・利用に関わる諸形質について研究を展開しています.北白川追分町の農学部敷地内にある京都農場の果樹園・実験圃場で,カキやウメ,モモをはじめとして,様々な果樹を栽培しながら研究材料として利用しています.特に約40aのカキ園には174品種246個体のカキが保存されており,国内外で最大級のカキ品種保存園として知られています.
「桃栗三年柿八年」の故事にもあるように果樹の開花には長い年月がかかり,また一個体のサイズも大きいので,研究には長期間を要します.そのようななか,果樹の重要農業形質に関して地道な研究を続けています.研究材料としては扱いにくい木本性作物を研究対象としていますが,最近では地道に続けてきた研究が,農業と農学(自家和合性選抜マーカーの開発,休眠制御機構に関する研究,自家不和合性に関する研究)や植物科学(雌雄異株性の性決定因子を植物で初めて柿において発見)の発展に資する多くの画期的な成果を生み出しています.また新品種の育成と利用法に関する研究にも力を注いでいます(ベビーパーシモンプロジェクト).果樹園芸学研究室では,果樹園芸産業の発展を見据えた研究が基礎科学にも貢献する知見をももたらすように,常に両者のバランスを考えながら研究を展開しています.
果樹園芸学研究室の教育・研究活動
農学専攻ミッションに基づいて,教育・研究活動をすすめていきます.果樹産業の発展に貢献し,研究成果を積極的に発信し,諸外国の研究者と交流を深め,世界における果樹産業の発展に貢献していくことを目指しています.
果樹を対象とする研究は,「大学」・「国の研究機関(果樹研究所)」・「都道府県の試験場」で行われていますが,この中において「大学」の研究は,基礎生物学分野への貢献や革新的技術創出のための基礎的研究も担っています.研究成果は,主に園芸学会(Japanese Society for Horticultural Science),あるいは国際園芸学会(International Society for Horticultural Science)が主催する各種国際シンポジウムで発信しています.
学生のみなさんには,本研究室で果樹の生理・生態,分子機構解明,新技術開発などの研究に携わる過程で「考える力」を養い,国際舞台で研究成果を発表するなどして「国際感覚」を養ってもらいたいと考えています.
果樹園芸学研究室の歴史
初代の菊池秋雄教授(教授期:1926年~1943年)は,明治から大正にかけて西洋から導入された多くの果樹類の生理・生態学的研究を行いました.ニホンナシの品種改良およびその主要形質の遺伝に関して長年研究を続け,「偏父性不親和(交雑組み合わせによって,交雑実生の半数の個体は父親品種と不親和となる)」現象を見いだすなど大きな業績を残しました.育成された新品種のなかでも黒斑病抵抗性があり品質のすぐれる‘菊水’・‘八雲’・‘新高’は特に有名です.‘菊水’は現在の人気品種‘幸水’・‘新水’の親品種として利用されました.日本の果樹園芸学の黎明期を支え,数々の名著書を残したことでも有名です.
小林 章教授(教授期:1948年~1973年)は,戦後の果樹園の復興期で果樹の栽培面積が飛躍的に拡大していった時代の果樹園芸学を支えました.果樹の温度環境・栄養生理・土壌環境・光環境に関する研究を進めました.特にブドウの日長反応性や果実の肥大・成熟・品質に及ぼす温度の影響について調査した結果は,ブドウ適地の選定や施設ブドウの温度管理の実際に大きく貢献しました.
苫名 孝教授(教授期:1973年~1986年)は,果樹産業が量的生産から高品質果実の生産へ転換し,施設栽培が急増していった時代の果樹園芸学を支えました.特に果実温度と果実の発育・成熟に関する研究を進めました.果樹生産を目的とする果樹園芸にあっては果実の生態を一義的に考えるべきであるとの立場から一連の主要果樹を対象に研究を進めました.
杉浦 明教授(教授期:1986年~2002年)は,カキの脱渋性に関する研究を精力的に進めました.完全甘柿と不完全甘柿という2種類の脱渋機構の存在を明らかにするとともに,樹上脱渋方法を考案しました.この技術は和歌山県のブランド柿「紀ノ川ガキ」に応用されています.また,カキの組織培養技術開発や胚乳培養による倍数体育成法も開発しました.
米森敬三教授(教授期:2002年~2015年)は,カキ属や熱帯果樹の系統分類やカキのタンニン蓄積機構に関する研究を進めました.米森教授が開発したカキの甘渋性判別マーカーは,甘柿育種における選抜マーカーとして育種現場で利用されており,甘ガキの新品種の育成に有効利用されています.